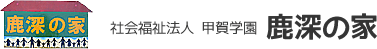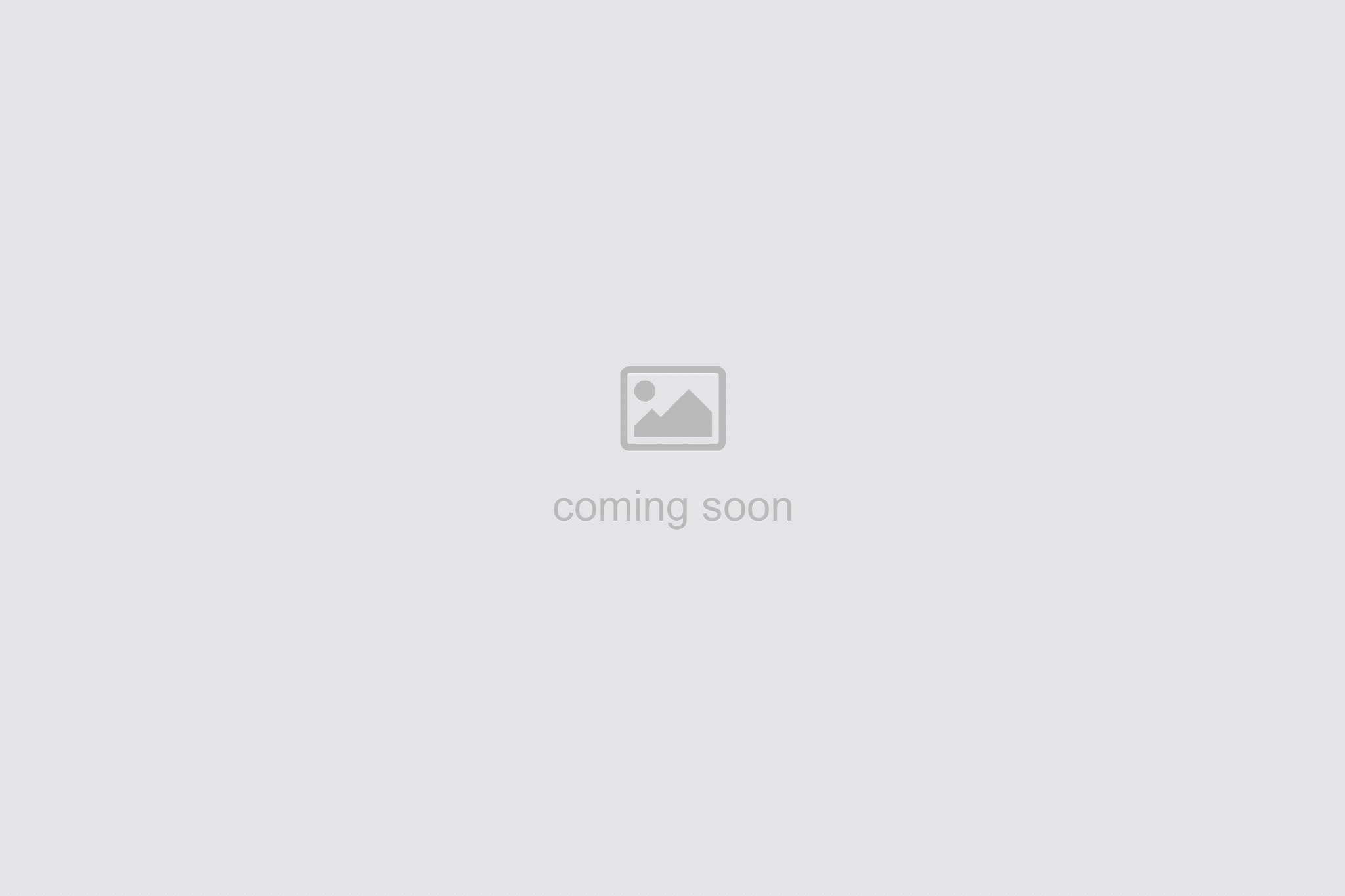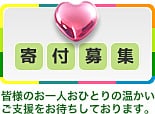児童養護施設 鹿深の家
鹿深の家基礎セミナー2024
5/13、児童養護施設 鹿深の家の体育館にて「鹿深の家基礎セミナー2024」を開催いたしました。
厚生労働省(2022)に公表された児童養護施設入所児童等調査(平成30年2月1日現在)によると児童養護施設に入所する子どもたちの65.6%は虐待を受けた経験があり、36.7%の子どもたちには発達に何らかの障害を抱えているとされています。
そのため、児童養護施設における養育には非常に高度な専門性が求められるようになっています。
こうした「要保護児童」の支援、すなわち、愛着障害・複雑性PTSD・神経発達症・性問題行動等を有していることが少なくない子どもたちとの関わりに難しさを感じているのは何も児童養護施設の職員だけではありません。
そこで、滋賀県下の要保護児童に関わる若手職員の資質向上と、若手職員が安心・安全を感じ展望を持ちながら働き続けるための一助となるようなネットワーク形成を図るべく企画したのが「鹿深の家基礎セミナー」です。
おかげ様で当初の募集定員を大幅に超える(1.5倍!)受講申込があり、多くの方にご参加いただけました。
アンケートの声を一部紹介いたします。
「4つのテーマ、それぞれに切り口は違いましたが、どの講義も最後は『目の前のその子なりの安心・安全を保障する』というところに行きついており、しっかりと縦糸が一本通っている感じで、そのことがとても印象に残りました。4つのテーマの順番も基礎から応用へと広がっていく感じがあり、参加していてとてもイメージしやすかったです。」
「入職してまもなくのこのタイミング、悩める時期にベテラン職員の実践を聞け、これから目指すべき道しるべが浮かび上がってきたように思う。今回教えていただいたことを忘れず、日々子どもたちと関わっていきたい。」
「他の施設の方々と交流できたのが楽しかったし、物事を様々な視点から考える機会になって良かった。下がりつつあったモチベーションが少しアップした。」
ご参加いただいた皆さま、講師を務めてくださった先生方、本当にありがとうございました!!!
児童養護施設 鹿深の家 綱島 庸祐
「鹿深の家の「ふつう」の子育て 人が育つために大切なこと」刊行記念トークイベントに寄せられた感想について
ご参加いただいた方々の感想をいくつかご紹介いたします。
○ 豊富な経験を持たれている方々でもまだまだ多くのことに悩み、考え続けておられるのだなと感じ、
「みなさん同じなんだ」という安心感を持てました。また、この仕事の奥深さ・楽しさを改めて感じて
今とてもワクワクしています。
○ 支援者側の思い、感情、葛藤といった「生」の部分をたくさん聞かせていただき、同じ施設職員として
安心しました。答えがないことだからこその「対談」という形だったのだと思い至りました。
○ 書籍もトークも専門用語ではない言葉で多く語ってくださったので、専門外の私でもとても分かりやす
かったです。多くの「生」の言葉が響きました。
○ 「偽善者になっているのではないか?」と自問している点が素晴らしい。
○ 「子育ては自分育て」だということを改めて感じさせられる時間でした。
○ 現場の職員の思いをリアルに書いてくださったことで救われている職員(同業者)がたくさんいるだろう
なと強く思いました。「こんなこと思っていいのかな?」「こんなこと思っているのは自分だけ?」と
いったモヤモヤが晴れるだろうなと思いました。
○ 理論的な話ではなく、日々子どもたちと実際に関わっておられる職員の方たちの生の話をたくさん聞く
ことができ、自分自身ももっと肩の力を抜いて関わっていっていいのだなと思えました。とても勇気
づけられました。
○ 「行きつ戻りつ」を含め、子育てにおいて大事にされていることがとてもよく伝わってきました。
私は教師ですが通じる部分がたくさんあることを感じました。
○ 「愛情=子どもの生活に興味を持つこと」等、ひとつひとつの抽象的な事柄を、より具体的な言葉に
して定義しようとされているのが素晴らしいなと思いました。
○ 職種を問わず色んな大人たちがいて、その人たちがその人らしさを発揮しながら子どもの傍にいること、
それが子どもの安心して育てる素晴らしい環境を形作っているのだと実感しました。
○ 幅のある関わりの中で人は育つということ、本当にその通りであると感じました。
○ 鹿深の家のみなさんは、まさに個性あふれる素敵な大人たちだと思います。
○ 施設全体で子どもを抱えている感覚、本当に見習いたいと思いました。
○ 子育てというのは「こうあるべき」という堅苦しいものではなく、幅があって当然で、それを「ふつう」
だと思って良いのだということを強く感じました。
○ いろいろな場面で狭い「あるべき姿」を求められているうちに、自分も知らず知らず疲れていたのだと
気付き、元気をいただきました。
○ 「児童養護施設職員としての仕事のあり方とは?」という話題になった際、「(その子その子のニードに
即した役割を)演じる」と「素の自分の弱い部分をさらけ出していく」という両方の意見が同じ施設の
職員さんから出ていたのが面白かった。両方本音だと思う。こういうやりとりができることこそが鹿深の
家さんの強みなのではと感じた。
○ 養育で大切にされていることをこのように整理されて伝承していくことが施設養育の価値なのだと、素敵
なモデルを見させていただきました。
フットサル
令和5年度近畿児童福祉施設スポーツ大会
近畿大会結果 10位
近畿大会では12チームが出場しました。
結果は1勝4敗で10位でした。
また来年に向けて頑張っていきます!
<過去の近畿児童福祉施設スポーツ大会における成績>
第48回(平成11年度) キックベース 第3位
第55回(平成18年度) フットサル 優勝
第56回(平成19年度) フットサル 準優勝
第57回(平成20年度) フットサル 準優勝
第58回(平成21年度) フットサル 第5位
第61回(平成24年度) フットサル 準優勝
第62回(平成25年度) フットサル 優勝
第63回(平成26年度) フットサル 優勝
第64回(平成27年度) フットサル 準優勝
第68回(平成31年度) フットサル 本選出場
第71回(令和5年度) フットサル 本選出場
※令和4年度は県予選を突破しましたが、新型コロナウイルス感染症により、大会が中止となりました。
環境を活かした取り組み
鈴鹿山脈を望む丘陵地帯に位置し、緑に囲まれ、草花が咲き、小鳥のさえずる風光明媚な自然環境の中で子ども達は生活しています。広大な敷地には、グラウンドや体育館(地域交流施設)があり、学習・スポーツ・余暇活動に取り組める設備が充実しています。




小舎制養育の推進
サービス評価委員会の開催
子ども達の生活環境改善のために、不定期に開催される委員会です。子ども達は興味のあるテーマの委員会に自主的に参加します。この取り組み自体は、平成19年から始まりました。当時は、施設内にある暗黙のルールについて明文化し、自分たちの暮らしを客観的に見つめ直してみようという趣旨のもと、「施設生活のしおり」づくりを行いました。この過程の中で、多くのルールの存在や、ルールが出来上がった背景や理由がよく分からないという事態など、多くの課題を確認することができました。
最近は、携帯電話の所持やホーム間格差(日課の違い)などについて意見交換が行われ、およそ1年の議論を経て携帯の所持が認められた事例などがあります。この委員会の取り組みを継続している中で、「大人に言ってもどうせ何も変わらない」という諦めの気持ちから、「サービス評価委員会に参画することによって何か変わるかもしれない」という少し前向きな気落ちに変わってきています。施設の相互交流
平成27年の8月から沖縄県の児童養護施設「石嶺児童園」との交流が始まりました。今年で3回目です。グラウンドにテント設置し泊まってもらったり、たこやきパーティーを開催したり、ボランティアで焼きソバを作って下さる方が現れたりと、少しずつ中身が整ってきました。
初めて本州に渡ってきたという子の「イチョウの木の本物を初めて見た。これって本当に黄色くなるんですか?」という質問がとても印象に残っています。
この3年間は先方から来てもらうだけでしたので、鹿深の家の子ども達をいつか沖縄に連れて行きたいなと考えています。
人材育成の取り組み
子どもの育ちを支える人材を育成するために、職場内研修をはじめ、外部研修に積極的に職員を派遣し、さまざまな機会を提供しています。また、外部の有識者を施設に招き、ケースカンファレンスやグループワークを実施し、見立てる力や対応のバリエーションを学ぶ機会を設けています。
研修体系の一例
<職場内研修(内容)>
『この子を受け止めて。育むために』の購読会・社会的養護の基礎知識・こころとからだの安心安全プログラム(性教育)・接遇・事務処理・措置費・食育・里親・心理・記録のとり方・児童相談所の巡回指導員との面談 など
<職場外研修(主催団体)>
全国児童養護施設協議会・近畿児童養護施設協議会・滋賀県児童福祉入所施設協議会・“人間と性”教育研究協議会・小舎制養育研究会・子どもの虹情報研修センター・SBI・資生堂児童福祉海外研修・NPO STARS主催研修 など
<その他>
当施設では、毎年1回3つのグループに分けて、国内外の児童福祉施設や教育機関、企業などの訪問を行う宿泊研修に力を入れています。
Brother & Sister制度の導入
新人職員の悩みの一つに「誰に相談したら良いか分からない」というものがあります。職員の孤独感はやがて職場内の人間関係の悪化や心身の変調、さらには退職へと繋がっていく、非常にリスクの高い課題だと言えます。
そこで当施設は、新人職員一人に対し、勤続年数2~3年の職員を一名・勤続年数5年以上の中堅職員一名を配置し、新人職員の身近な相談相手として、教育係として、当制度を導入しています。
地域交流
CFRびわこ(虐待防止啓発活動を行う市民団体)とのコラボ

2016@能登川付近
CFRびわこは「Children First Run」の頭文字です。
毎年11月の児童虐待防止推進月間を前にびわ湖一周オレンジリボ ンたすきリレーを開催。主に滋賀県内で開催されるマラソン大会に参加し、走りながら、応援しながら、オレンジリボンを多くの人に知ってもらう活動や駅・商業施設などで街頭啓発を行うことで、児童虐待防止を呼びかけています。
保育士、教員、施設職員、児童福祉司など子どもに関わるものを中心に平成22年2月6にち立ち上げ。会員は約140名。
保育士、教員、施設職員、児童福祉司など子どもに関わるものを中心に平成22年2月6にち立ち上げ。会員は約140名。